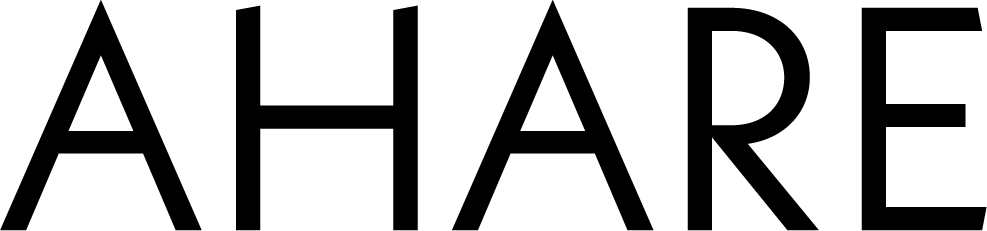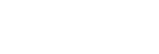森に一歩踏み入れると、そこに棲む生きものたちは、すでに私たちの気配を察知している。人と自然の間には、言葉では触れられない境界があるのかもしれない。
私たちの持つアイデンティティには、"無"が在るとされている。
それらは、情緒の瞬間であり、現象とも言えるのではないか。
日本的感性を最もよく体現するひとつに挙げられる日本庭園は、自然界を模した"借景"として築かれてきた —— つまり、人々はそれらを美の形式としながら、自然を捏造し、構築してきた空間と言える。
本展では、「庭を模した庭」を創造する。
平安時代後期以降に書かれた庭作りの書「作庭記」にみられる生得の庭。
受け継がれてきた文脈のほんのひと握りを空間へしつらえた。外の庭と情報を共有する作品が配置され、あたかも"それ"が在るように仕向けた。
ここで主題となるのは、視えることのない風景への入口であり、知覚の扉である。
香りが導くのは、"モノ"そのものではなく、それによって引き起こされる感覚体験の鍵である。
この知覚の庭では、空間内に3つの香りがレイヤリングされ、回遊することで得られる体験者それぞれが視る借景へと辿り着いたのではないか。
私たちが創り出す香の建築は、目には見えない。
この小さな「 知覚の庭 」に立つとき、
そこに風は吹いているか。